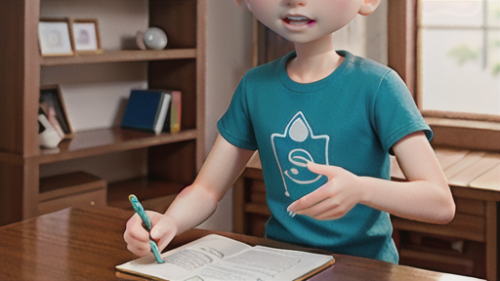経済指標
経済指標 全国消費者信頼感指数:暮らし向きを測る尺度
全国消費者信頼感指数は、英国の住宅金融機関が発表する、消費者の経済に対する信頼度を示す指標です。毎月、金融政策委員会の開催前に公表され、消費者が現在の経済状況や将来の見通しをどう感じているかを数値で表します。この指数は、消費者の支出意欲や貯蓄意向を予測する上で重要であり、英国経済の健全性を測る上で欠かせないバロメーターとされています。算出方法は、米国の調査会社が用いている集計方法を基に、独自の調査を実施しています。金融市場や企業の経営者は、この指数を将来の経済動向を予測するための重要な情報源として活用しています。発表は通常、金融政策委員会の前の水曜日に行われ、市場関係者は固唾をのんで見守ります。なぜなら、この指数の変動が、イングランド銀行の金融政策に影響を与える可能性があるからです。そのため、全国消費者信頼感指数は、英国経済の動向を把握し、将来の経済状況を予測するための重要な指標として、広く認識されています。