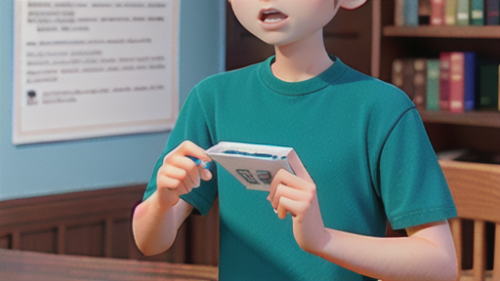金融政策
金融政策 市場から資金を吸い上げる:売りオペレーションとは
売り出し操作は、中央銀行が市場の資金量を調整するために行う公開市場操作の一つです。これは、市場に余剰資金が多い場合に、その資金を吸収し、通貨の価値を安定させる目的で行われます。具体的には、中央銀行が保有する国債などの有価証券を市中の銀行に売却します。銀行はこれらを購入するために資金を中央銀行に支払うため、市中に出回るお金の量が減少します。この操作は、物価の上昇を抑えたり、自国通貨の価値を維持したりするために用いられます。反対に、市場にお金を供給したい場合には、買い入れ操作という手法が用いられます。中央銀行は、経済の状況や目標に応じて、これらの操作を使い分け、金融政策を調整します。この操作は金融市場において重要な役割を果たしており、その影響を理解することは、経済全体を把握する上で欠かせません。