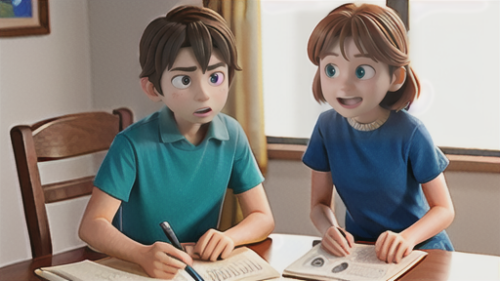経済政策
経済政策 関税以外の貿易障壁:その実態と影響
非関税障壁とは、関税以外の手段で国際的な取引を制限する多岐にわたる措置の総称です。関税は輸入品に直接課税するものですが、非関税障壁はより複雑な形で貿易に影響を与えます。例えば、輸出に対する政府の補助金、政府による調達における差別、煩雑で不透明な税関の手続き、商品の品質や安全基準などが挙げられます。これらは、外国製品の流入を妨げ、国内産業を保護する可能性があります。輸入量の制限や、自主的な輸出規制、輸入時の保証金なども非関税障壁の一例です。非関税障壁は、消費者の選択肢を狭め、価格を上昇させるだけでなく、国際競争を阻害し、経済成長の鈍化を招くこともあります。近年、関税引き下げが進む中で、非関税障壁は新たな貿易障壁として注目されており、国際貿易交渉において重要な議題となっています。