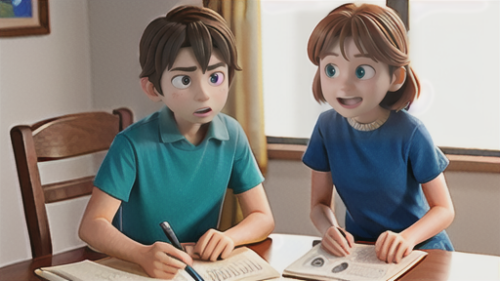経済指標
経済指標 次世代を担う十一の国々:ネクストイレブンとは
ネクストイレブンとは、二千七年に米国の金融機関であるゴールドマン・サックスが発表した経済に関する報告書で示された、将来的に高い経済成長が期待される十一の新興国を指します。当時注目されていた、伯剌西爾、露西亜、印度、中華人民共和国という、いわゆる新興四か国に次ぐ成長の可能性を秘めた国々として選ばれました。具体的には、イラン、印度尼西亜、エジプト、大韓民国、トルコ、ナイジェリア、パキスタン、バングラデシュ、比律賓、越南、そして墨西哥の十一か国が含まれます。これらの国々は、それぞれの地域において重要な位置を占めており、人口、資源、地理的な利点など、多様な成長要因を有しています。これらの国々が将来的に世界の経済秩序において、より大きな影響力を持つようになると予測されています。ネクストイレブンという概念は、単なる経済予測にとどまらず、投資家や政策立案者にとって、新たな成長市場を検討する上での重要な指標となりました。今後の世界の経済動向を予測する上で、ネクストイレブンの動向は、引き続き注目されるでしょう。