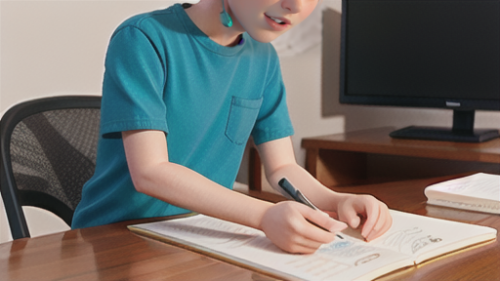金融政策
金融政策 金融庁による横断的検証とは何か?
我が国の金融行政において横断的検証が導入されたのは、金融市場の複雑化と高度化が背景にあります。従来の金融検査は、各機関が法令を遵守しているかを確認するものでしたが、グローバル化が進む現代では、それだけでは金融システム全体の安定を確保できません。そこで金融庁は、金融機関全体のリスク管理体制を把握し、より効果的な監督を行うために、この手法を導入しました。これは、業界全体の優れた事例を共有し、業界全体の水準向上を図ることを目的としています。また、金融機関が共通して直面する課題や危険を早期に発見し、適切な対策を講じることで、金融システムの安定性を高めることが期待されています。従来の検査では見過ごされがちだった、金融機関間の相互関係や、特定のテーマに関する業界全体の傾向などを把握する上で、横断的検証は有効な手段です。金融庁は、この検証を通じて金融機関の自主的な改善を促し、健全な金融システムの構築を目指しています。